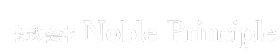今回は、米国のトランプ政権に関してのコメントです。
トランプ政権1.0の時も、不規則発言で金融市場はかなり、混乱した記憶があります。
関税に関しては、対中関税が主体で、外交面ではそれ程、混乱しなかったように思います。
また、内紛が生じたとは言え、政権内に実績のある閣僚が存在し、一定のブレーキ役を果たしていました。
ただ、今回は、就任後まだ、2ヶ月程度ですが、通商政策、つまり、相互関税の導入や幅広い物品が関税の対象になる等、今後の経済への悪影響が懸念される展開になってきています。
また、外交面でも、ウクライナ問題、中東問題等の対応に何とも言えない印象があります。
パナマ運河接収、グリーンランド併合、カナダへの51番目の州とのコメント等、結構、理解に苦しむ言動が見られます。ウクライナのゼレンスキー大統領との会談で、米国は同盟国であっても、軍事的な支援は限定的という印象を世界的に広めてしまいました。
結果、ドイツは軍事予算を策定、フランスも核の傘の議論を進めています。
カナダに対する関税や言動で、かなり、カナダサイドは強硬なスタンスになってしまいました。ビジネスや通常の生活でも同様ですが、人と人の関係の場合、ケンカや口論をするにしても、関係の修復が可能な範囲で対応するのが、一般的だと思っています。こじれにこじれてしまうと、修復が困難になることも少なく無いと思います。欧州の一部の国やカナダは、かなり本気でお怒りの印象です。大国の言いなりにならず、国益を重視する姿勢に感服します。
実際には、関税にしても、外交にしても、俗人が理解できない深い配慮や戦略があるのかもしれませんが、少し、心配です。
ロシアのウクライナ侵攻に関するホワイトハウスでの会談を見た印象ですが、個人的には、ゼレンスキー大統領が気の毒に感じました。また、停戦に関しても、当事者を外して、米露だけで話を進めるというのは、如何なものか?という印象です。
ここからは、全くの妄想ですが、
仮に台湾有事が生じた場合、沖縄等の米軍が軍事行動を取るかどうかと疑念を感じます。
米軍が動かない場合、自衛隊の支援も限定的にならざるを得ないように思います。
その場合、ロシアがそれを見て、米軍が同盟国の防衛に消極的と判断すると、北海道に侵攻する可能性が高まるのでは?とも感じてしまいます。オホーツク海から北海道に接近し、日本を挑発したとして、米軍三沢基地が動かないと判断できると、ウクライナの二の舞になる可能性を懸念します。
ウクライナ問題やNATOの資金支援などの米国政権の対応によって、ドイツやフランスが離反し、独自の防衛のスタンスに変化させました。日本の場合も、今後、日米安保や憲法改正等も議論になってくるかもしれませんね。トランプ政権は、各国の防衛は各国で対応すべしというスタンスのようですが、その場合、従来の日米安保の前提が瓦解する可能性も考えられます。
極端な視点ですが、憲法改正や自衛隊の軍備強化を行っていくことになったとしても、人的な兵力が乏しいのがネックです。軍備強化のための徴兵制導入等となると、現実的ではありませんね。いずれにしても、僅か2ヶ月の期間ですが、外交や防衛に関しても、深く考えさせられることが増えてきました。
次は、政府効率化に関しての私見です。
財政悪化を防ぎ、財政再建を目指すという趣旨には、賛同します。
が、話の進め方や失業への影響に対する配慮が欠けているように感じます。
外資系企業では、解雇は普通に存在しますが、事前に警告を伝えたり、猶予期間を設けたりすることが一般的です。また、解雇に該当する人を選別するにしても、より慎重な対応が取られます。トランプさんなのか、イーロンマスクさん主導なのかは、わかりませんが、本当に必要な人まで解雇してしまい、機密事項が漏れることや業務遂行が困難になることもありそうで、気になってしまいます。
米国の経済指標は、3月に入って、徐々に悪化するものも見られるようになりました。
相互完成の発効が4月2日に予定されていますから、5月以降の消費者物価指数やPCEコアデフレータの悪化が見られるかもしれません。今年に入って、米国株式市場は下落が続き、厳しい展開になっていますが、現実の指標が悪化することで、よりリスクオフが進むことも心配です。政府効率化によって、連邦政府関係者だけでなく、発注先企業の人員削減も加速しているようです。それに加え、移民政策の厳格化によって、低賃金労働者が不足することも考えられます。農業や単純労働の現場では、移民の労働者が占める割合がかなり高いようです。低賃金の労働に米国の労働者の方々が就労するとも考えにくく、これも賃金上昇を通じ、インフレ拡大になる可能性を感じます。
一部の意見では、「米国債の借換え時期を控え、株価下落を通じ、長期金利低下を狙っているのでは?」というものもあるようです。仮に、その通りだったとしても、株価下落や景気低迷等の副作用が大きすぎるように感じます。FRBは、利下げスタンスですが、インフレが再加速すると、長期金利に上昇圧力がかかり、低利での借換えができなくなる可能性もありますね。また、事実として、低利での借換えという目的を他国が理解すると、報復として外貨準備で保有している米国債の売却をちらつかせるかもしれません。米国債売却は、もちろん、金利上昇要因となります。ケンカの仕方を間違えると、相手が予想以上に強硬になり、不測の事態を招く可能性も考えて欲しいところです。
トランプ政権発足、約2ヶ月の政策を他国の一市民の立場では、心配する必要は無いのかもしれませんが、他国も混乱に巻き込んでいる点を憂慮します。また、経済も外交も同盟関係も時間をかけて、世界の多くの先人の努力で現在の姿になったことを考えると、心配の種は尽きません。場合によっては、今後、米政権が変わっても、不可逆的な展開(元に戻れない)になって、安定した国際関係や経済環境維持が難しくなるかもしれません。
以前のブログでも触れましたが、今後は、外交、経済政策、身近なところでは、投資戦略なども、地政学や経済安保などのリスク要因を前提に考えていく必要がありそうです。
もちろん、米国も他国も含んだグローバル経済が改めて、安定化していくことを所望します。
次回は、「ゴールド(金)投資について」の予定ですが、来週は都合により、休載させて頂きます。
当ブログは、毎週金曜日に更新予定です。
金曜日が休日の場合は、お休みします。
いつもながら、投資に際しましては、自己責任でお願いします。
内容、ご相談に関しましては、株式会社 Noble principleまでお問い合わせください。
尚、HP下部にInstagramのリンクを用意させて頂きました。
基本的に毎日、日米の金融マーケットに関する投稿、不定期で投資やライフプランに関する投稿をしています。是非、ご覧ください。