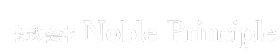年末が近づき、来年の新NISAが気になってきます。
今回は、新NISAに関して、制度的なチェック項目と投資してみたい資産に関してのコメントです。また、ボリュームがかさみ ましたので、今週と次週に分けて掲載します。
新NISAは、毎年の投資枠や総投資枠の上限があるものの、非課税制度が恒久化されます。
資産形成層が将来に向けて資産を作る、また、資産保有層が配当などのインカムを確保するなど、目的に応じた戦術が考えられます。
因みに、現在の税制では、キャピタルゲイン(実現益)、インカムゲイン(配当、普通分配金など)に対して、20.315%の課税がなされます。新NISAは、これらが非課税となるありがたい制度です。但し、後述の通り、米国株の配当は、現地の10%課税は回避できません。
新NISAの活用には、仕組みや制度の理解は欠かせませんので、今回は、思いつくまま、そちらを中心にコメントします。
何度か、このブログでも紹介していますが、再度、ポイントを列挙してみます。
2023年11月現在の情報で、今後、変更があり得ることをご承知ください。
■保有期間が無期限とされること
■年間非課税枠がつみたて相当分が40万円から120万円に、一般枠相当分(成長投資枠)が120万円から240万円に拡大したこと、(生涯非課税投資枠が1,800万円、うち成長投資枠が1,200万円)です。(年間投資枠:120万円+240万円=360万円)
■つみたて相当分は、インデックスファンドのみ、成長投資枠は、個別株式、ETF、その他の投資信託など幅広い対象となります。
■投資した有価証券を売却しても、将来、投資枠が復活します。但し、生涯投資枠は変わりません。
■同一年度、一人、一口座(一金融機関)しか、口座開設できません。
金融期間の変更は可能です。但し、手間がかかります。
■必ずしも、満額投資する必要はありません。可能な範囲でも十分です。
■個別株式に投資を考えている場合は、証券会社の口座開設が必要になります。
■米国株、米国ETFの配当は、現地の税金が非課税になりません。
まず、制度設計についてコメントしてみます。
投資枠は、つみたて相当分が年間120万円、一般相当分が240万円、合計360万円が年間の上限となります。生涯投資枠は、1,800万円です。毎年、満額投資して5年間継続すると、生涯投資枠に達することになります。年間投資枠の上限や年間投資枠の上限は、変わりませんが、売却した場合、将来に投資枠の復活がある点も見逃せません。
つみたて相当分に関しては、限定された投資信託(インデックスファンド)だけが対象となります。あくまでも、沢山ある投資信託の一部だけが対象です。
一般相当分(成長投資枠)は、内外の株式、ETF、つみたて相当分よりも幅広い投資信託が対象で、選択肢が多い枠となっています。つみたて相当分と同じ投資信託でも対象であれば、もちろん、投資可能です。
つみたて相当分対象の投資信託は、信託報酬、運用対象、わかりやすさなどの複数の項目をクリアしたインデックスファンドとされており、現状、オーソドックスなタイプだけが、対象になっていて、思ったよりも種類が限定されている印象です。
具体的には、国内株なら、日経225、TOPIX、海外株なら、米NYダウ、S&P500、NASDAQ、全世界株式、新興国株式などの値動きに連動するインデックスファンドです。各金融機関のHPなどで、どのファンドが積み立て枠に該当するか、開示されています。あわせて、成長投資枠の対象ファンドも開示されていますね。成長投資枠の投資信託に関しては、個人的にほとんどのファンドが対象になると思っていましたが、結構、選抜されている印象で、対象外のファンドも少なくありません。
基本的な投資戦術としては、ベースの資産形成は、つみたて相当分で、インデックスファンドを通じて長期投資を行い、プラスアルファを成長枠で狙うという考え方が一般的でしょうか?
投資経験の少ない方の場合は、成長枠でもインデックスファンドという選択も有効だと思います。S&P500や全世界株式などの指数は、世界経済の成長に概ね連動します。長期的な成長を考えれば、個別銘柄で大当たりを狙うよりも、安定性は高いようにも感じます。安全性ではありませんので、悪しからず。
また、比較的、一般の方も指数の値動きを把握しやすい面もメリットですね。
成長投資枠で個別株式(国内株、海外株)に投資する場合、現状では、証券会社に口座開設をしないと株式には投資できません。銀行などの金融機関では、新NISAで、投資信託への投資は可能ですが、株式については、不可です。(2023年現在)逆に言うと、証券会社では、株式も投資信託も選択可能です。
現時点で投資対象が投資信託だけで良いという方にとっても、将来的に株式の個別銘柄投資も視野に入る可能性を考えた場合、証券会社の口座開設が望ましいと感じます。一旦、口座開設した後、新NISAの金融機関を変更することは可能ですが、手間と時間はかかります。
海外個別株式に関しては、国内株同様、証券会社だけが対応できますが、NISAに対応しているネット証券がある一方、現状ではNISA未対応の証券会社もあるようです。米国株式にも魅力的な銘柄が多いので、要確認ですね。
また、株式投資の場合、配当金を非課税で受領するためには、証券会社の口座に配当金が入金される「株式数比例配分方式」にする必要があります。現行NISAでも同様ですが、このやり方にしないと、非課税になりません。尚、投資信託の分配金は、受け取り方法にかかわらず、非課税です。
仮に複数の証券会社に口座がある場合、一社で手続きすれば、全社対応できるようですね。
また、各社の預かり証券に応じた配当が各社の口座に入ることになります。
留意点として、米国株式やETFの配当に関して、現地の10%課税は、NISAでも非課税にはなりません。国内分の課税は非課税です。配当利回りがあまり高くないケースでは、影響は軽微ですが、高配当の銘柄については、負担もバカになりませんね。
因みに、通常の特定口座の場合は、確定申告を行うことで、一定の範囲で海外課税分の還付も可能です。(外国税額控除)
また、新たに金融機関にNISA口を座開設するにあたり、年末から年明けにかけて、かなり、申込みが集中する見込みのようで、時間がかかる可能性があります。
つみたて相当分の投資は、ボーナス設定もできるケースもありますが、基本的には毎月、一定額を積み立てることになります。また、成長枠に関しては、適宜、(年始から年末までの間、自分のタイミングで)投資することになります。
今週は、新NISAの制度について思い当たることをまとめてみました。
いずれにしても、税制面で非常に有利な制度なので、株価変動リスクや為替リスクなどを踏まえた上で、是非、検討したい投資です。
次回は、個人的に考える投資戦略についてコメントしたいと思います。
当ブログは、毎週金曜日に更新予定です。
金曜日が休日の場合は、お休みします。
いつもながら、投資に際しましては、自己責任でお願いします。
内容、ご相談に関しましては、株式会社 Noble principleまでお問い合わせください。
尚、HP下部にInstagramのリンクを用意させて頂きました。
基本的に毎日、日米の金融マーケットに関する投稿、不定期で投資やライフプランに関する投稿をしています。是非、ご覧ください。