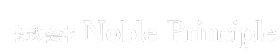今回は、インフレについてのコメントです。
日米を始めとして、相変わらず、グローバルでのインフレが落ち着きません。
そもそもの経緯は、コロナショックでサプライチェーンが寸断され、供給サイドの目詰まりで、供給不足が背景とされています。その後は、ロシアとウクライナの紛争から、ウクライナの農産物の供給が滞ったことも影響しています。
インフレは、物価が上昇することを意味しますが、デマンド・プル型とコスト・プッシュ型に区分けされます。背景が需要の問題か、供給の問題かという視点ですね。
デマンド・プル型というのは、
デマンド(需要)が増加し、消費者の購買意欲が高まることや企業の設備投資意欲が高まることから、需要が増加することで物価が上昇することを意味します。このケースでは、経済成長が促進されます。
企業は値上げをすることにより、売上げや利益が増加します。結果として、生産量が増加し、賃金の上昇を通じて、消費を拡大し、経済の好循環を生み出すパターンです。
物価上昇とともに国民が豊かになるので、「良いインフレ」とされています。
日本の高度経済成長期が該当しますね。
物価上昇率が高く、高金利の中でも、一人当たりGDPは拡大してきました。
「今日よりも明日が豊かになり、今年よりも来年が豊かになる」という雰囲気だったようです。物価が上昇していても、賃金もそれ以上に上昇し、消費が促進されたと言われています。
次に、コスト・プッシュ型インフレです。
こちらは、原材料価格、賃金、エネルギー価格の上昇など供給サイドの課題を通じて、生産コストが上昇します。それによって、企業が製品やサービスの価格を引き上げ、その結果として物価が上昇する現象です。従って、需要の多寡や景気動向にかかわらず、物価が上昇することになります。
最近の日本では、政府が賃上げ要請をすることで、大手企業の賃上げが実現しました。
が、企業の設備投資や個人消費が活発といった印象はありませんね。
こちらは、「悪いインフレ」とされています。
インフレは、基本的に物価は上昇しますが、現金価値が減価するため、不動産などの実物資産や株式等の金融資産上昇につながりやすい傾向があります。
また、現金の価値が減価するので、金利が多少高いとしても借入れの実質価値は減少します。
一方、デフレは、ものの値段が下がり、経済規模が縮小します。物価が下がることは、一時的には、消費者にとってありがたいことですが、結果的には収入が減少してしまう負のスパイラルにつながります。以前、テレビのインタビューで、若い女性の方が、「ものの値段が下がるので、デフレ大歓迎!!」と言っていたのが印象に残っています。「そんなことないのにな!先々、大変になるのに」と感じました。
ものの価格が下落し、現金の価値が上昇します。従って、ゼロ金利であっても、それ以上に物価が下落することが多いので、現預金を保有することで購買力が上昇することも少なくありません。また、名目金利は低いものの、現金の価値が上がるので、借入れ負担は、実は上昇します。
日本でもデフレ時代、ゼロ金利だからと住宅ローンを組む方も多かったようですが、経済学的には、デフレ経済下では、借入れ負担は増加しているのです。
現在の中国もデフレで苦しんでいますが、日本も同様、なかなか、脱却することが難しいのが実情です。
結論として
現在の日本は、コスト・プッシュ型インフレで、悪いインフレであると思います。
企業の設備投資や個人消費もパッとせず、物価だけが上昇していきます。
積極的に自動車や住宅等を購入する方が多くて、需要過多で物価が上昇するのであれば、良いインフレなのですが、現状は、残念な状況と感じています。
日本の場合、好景気による良いインフレの時代は、実は、バブル時代まで遡らないと、該当する時期が無かったようにも感じます。
官民とも、抜本的な構造改革の必要性を感じています。
次回は、「ネット証券の口座乗っ取りについて」の予定です。
来週のブログはお休みします。
当ブログは、毎週金曜日に更新予定です
金曜日が休日の場合は、お休みします。
いつもながら、投資に際しましては、自己責任でお願いします。
内容、ご相談に関しましては、株式会社 Noble principleまでお問い合わせください。
尚、HP下部にInstagramのリンクを用意させて頂きました。
基本的に毎日、日米の金融マーケットに関する投稿、不定期で投資やライフプランに関する投稿をしています。是非、ご覧ください。